4年生
今日は、4年生の学年ミニ集会でした。先日、参観日で披露した2分の1成人式の縮小版を行いました。


特技発表です。


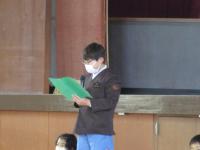


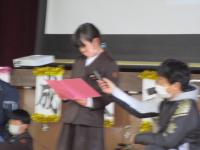
思い出発表では、生まれた時のエピソード、両親からのコメント、家族との楽しかった思い出、小学校生活での思い出などなど、それぞれの思いがたくさん詰まった心に残る発表でした。
校長先生から、「両親から生まれた皆さんは、星の数ほどいるけれど、だれ一人同じ人はいない。授かった自分の命を大切にしながら、精いっぱい生きてほしい。」というお話がありました。
10年間育てていただいた家族に感謝し、これからももっともっと成長してくださいね。
5年生



5年は、社会科「情報を生かした産業」の学習で、コンビニエンスストアでは、様々な情報が活用されていることを学びました。今日は、3校時に実際に見学に行ってきました。
見学に行くと、お忙しい中にもかかわらず店長さんやスタッフの方が質問に丁寧に答えてくださいました。ちょっと緊張気味の子どもたちでしたが、大切なことをメモしてきました。
この他、お店で実際に使っているタブレット端末やPOSレジスター、マルチコピー機をを見せていただきました。レジ打ち体験もさせていただきました。様々な勉強ができ、子どもたちは満足していました。
ファミリーマート玉川店の皆様、ありがとうございました。
5年生



5校時に来年度入学する1年生を迎えて、1年生と5年生が集会をしました。1年生や5年生が用意した歌やゲームで一緒に楽しみました。1年生からは手作りプレゼントもありました。心のこもった九和小らしい温かい集会になりました。子どもたちは、自分たちが上級生になることを自覚して、仲良くしようという気持ちを高めていました。来年度が楽しみです。
6年生



今日は、2月22日(水)のふるさとふれあいウォークに向けて、5・6年生が集まって事前打ち合わせをしました。ふるさとふれあいウォークとは、6年生の班長さんを中心としたたてわり班でふるさと玉川のよさを感じながら楽しく歩いたり、一緒に遊んだりする九和小ならではの恒例行事です。今日は、出発順のくじを引いたり、一緒に遊ぶ内容を考えていました。去年は、途中で雨が降って校内遠足になりました。今年は晴れますように。
今日は、今年度最後の参観日でした。どの学年も命や性について考える授業を公開しました。


1年生「だいじ、だいじ、どこだ?」


2年「おへそのひみつ」


3年「男の子 女の子」


4年「2分の1成人式」


5年「大人に近づく体」


6年「エイズについて知ろう」
成長には個人差があることや男女の違い、プライベートゾーンを守ること、自分の誕生の様子など、学年に応じた内容を学習し、命を大切にすること、一人一人が真剣に考え、自分を産み育ててくれた家族への感謝の気持ちを育んでいました。
1年生
国語科の学習「学校のことをつたえあおう」で、1年生は6人の先生方にインタビューに行きました。①ていねいなことばづかい②目を見てはきはきと という目標を持って、事前に用意しておいた質問をしました。



「失礼します。1年生の○○です。お話を聞きたいのですが、いま、よろしいでしょうか。」
子どもたちの表情は、緊張気味です。
「好きな食べ物は何ですか。」「休みの日は何をしていますか。」
質問を重ねると、先生たちの秘密の情報をゲットした子どもたちは笑顔になっていきました。



メモを取りながらも、質問をするときには、しっかりと相手の目を見て話すことができました。
明日は、先生インタビューでゲットした「先生の秘密」を伝え合います。ワクワクしますね。
1月31日の学びタイムは、6年生の学年発表ミニ集会でした。音楽でずっと取り組んでいた、「八木節」の合奏の発表でした。
この日のために、6年生は、音楽の時間の猛特訓に励みました。始めは、繰り返しが多くて、どこを演奏しているのか分からなくなったり、和の独特なリズムが覚えられなかったり、かなり苦労をしました。
しかし、次第にみんなの息も合ってきて、本番では、心を一つにみんなが全力を出して演奏を頑張りました。









合奏の後の感想発表では、「たくさん練習したのが伝わった。」「リズムが速くて迫力があった。」などのたくさんの感想が聞かれました。
5年生



6校時に代表委員会をしました。3月に行う「6年生ありがとう集会」の計画について話し合いました。お世話になった6年生に感謝の気持ちが伝わる集会にするために、出し物やプレゼントなどについて活発に意見交換していました。決まったことを実行するために、これから各学年で準備をしていきます。
2年生
今日、2年生は国語科の学習で、「かさこじぞう」の音読発表会をしました。
先週から、読む場面や役を決めたり、どんな工夫をして音読をするかについてそれぞれの班で話し合ったりしていました。
どの班もやる気がみなぎっており、「ここはじぞうさまが遠くにいるから、小さな声で読もうよ!」、「これはじいさまが悲しそうだから、悲しそうな声でゆっくり読もうよ!」と、たくさんの工夫を考えていました。身振り手振りを付け、気持ちを込めて一生懸命に音読練習をしていました。
そして、本番、どの班も気持ちを込めて、一生懸命に音読発表をしていました。そして、友達の音読の良かったところや上手だったところを発表しました。




最後には、タブレットで撮影した、自分たちの発表を見返して、音読発表会の感想を発表しました。
学級の全員が音読を頑張り、そして、全員が友達の音読の良かったところを見付けることができました。
3年生
3年生は「大好き!ふるさと玉川」をテーマに、総合的な学習の時間に学んだことを工夫して発表しました。
蒼社川の上流には龍岡や鈍川などの水源があり、アユやオイカワなどの魚たちがいることや、万葉の森がどのようにしてできたのか、玉川サイコーの方々に教えていただいたことを伝えました。そして、本校にも多くの樹木があり、それぞれ博士ちゃんたちがユーモアいっぱいに楽しく発表しました。
全校のみなさんや保護者の方々に見ていただき、子どもたちは大満足でした。「ふるさとの宝物を知ることができ、一生懸命発表していて感心しました」たくさんの感想をいただき、ありがとうございました。ふるさと玉川の一員として、今後もいろいろな活動を受け継いでいきたいです。




